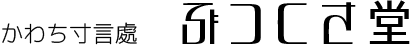6か月前、「見事にマンガしか読んでない少年_だった頃の話」と題し、いわゆる文芸書を読まずに大きくなった少年時代のことを投稿した。
高2の夏休み明けに提出したイアン・フレミングの『007は二度死ぬ』の読後感を、担任だった国語の教諭が「私も読んだ。ダブル・オー・セブンは面白い」と返してくれたことをふり返り、「心の広い、愉快な先生がいたのだった」と記した。そして、「中学・高校、国語の先生に恵まれていたのかもしれないね」と結んだ。―が、中2の夏休み明け「こんなウジウジゆうてる作品を読むのは、自分には苦痛でしかなかった」と書いた漱石の『こころ』の感想文については「趣旨は理解されたようだ」とさらりと流していた。―ので、今回はそちら、当時の国語の先生、Wさんとの印象的なエピソードを三つ書き留めておきたい。
W教諭は、小生の担任であったことはない。授業を受けたのは2年生の時からだった。
気に入られていたかどうかは知らないが、口が減らない口数の多い偏屈な少年だった私に、丁寧に接してくれていたような感じを覚えている。
W氏は既婚、教員夫婦だった。小さな町の、夫が中学校、妻が小学校の教師をしていた。
後にご本人から知らされたのだが、奥様は私の小学3年生の時の担任だったのだ。
小学3年の一年間は、私の小学生人生(笑)で最も低調だった一年で、担任のW先生とも友好的な関係を構築していた記憶がなく、むしろ、ソリが合わないヒビの入った関係だったように、当時から記憶している。
だからかどうかは不明だが、私自身の情報を良くも悪くも、奥様から多少インプットされていたのではないか、であるなら、以前からの知り合いのような接し方に納得がゆくのだ。
’65年(S41)の春か夏か、W教諭に「文芸部に入らへんか?」と誘われた。
『こころ』の感想文を読み小生の文才を評価した故のことなのかどうかは、季節同様定かではない(笑)
当時、W教諭は文芸部の顧問を務めていたようだが、その時の私はマンガと野球に夢中で、我が中学校にそんなものがあることすら知らなかったし、“文芸”というややこしいものにはとんと関心がなかったので、丁寧にお断りした。
その年の文化祭、どういう事情か不明だが、演目のひとつとして、学年選抜メンバーによる芝居を上演することになり、私もその一員にセレクトされた。(選抜委員はW教諭のようだった)
私は演劇には全く興味はなかったけれど、オフシーズン故か、生来お祭り好きなのか、10人ぐらいの中に混じって練習に参加した。
タイトルも内容も覚えていないが、私の役は町医者で、倒れている女性の脈を見るシーンがあり、「◯◯ちゃんの手ぇ握れてエエ役やな」と、演出者からも共演者からも冷やかされたことを覚えている。最も彼女は私のマドンナではなく、その点はわずかに残念ではあった。
私は中折れ帽を被りネクタイを締め白衣を着て舞台に上がった。
「私の 009 思い出話・下」(→)に登場したE君も警察官の役で制服を着用して出演した。
なるほど、芝居とはこんな風にして出来るもんなんかと、演劇制作のプロセスと多人数で何かを創るという事の骨格を教えてもらった体験だった。

第二のエピソードは、壇上で喋る経験。
これも昔のことで明瞭に説明できないのが歯痒いが、当時、年に一回「体験談発表会」という催しがあって、今でいえば「青年の主張」や「少年の主張」の如きイベントの田舎の中学校版みたいなものだったろう。
1966年(S42)、中学3年生の秋だったか冬だったか、その発表会のスピーカーに選ばれてしまった。
なんの“体験”もしていない私は、前年に石森章太郎の『マンガ家入門』に耽溺し、この年には『続・マンガ家入門』を目を爛々と輝かせて読み耽っていた時期だったので、自分のマンガ好きを読書体験のように言いくるめた作文を提出した。
曰く「マンガは芸術である」「マンガをバカにする大人たちよ、キチンと読んで論評せよ」的な、大上段に振りかぶった、その実、石森先生の受け売り丸出しの稚拙な作文だったと思う。
が、素材の目新しさで受けたのか、選ばれちゃったのだった。
500人とか1000人とかの前で、壇上で一人で喋る緊張感はそれなりに重圧だった。
この時学んだのは、自分をスケール以上に見せようとすると碌なことはない、ということ。_だったはず、しかし、以後、たびたび失敗しているなあ~。
中学校も卒業間近になった頃、私はW教諭に呼び出された。
「卒業文集とは別に、学校の文芸誌(誌名は失念した)に、マンガを載せよと思うねん。書いてみいひんか?」
マンガの執筆依頼、これが第三のエピソードである。
常々マンガを書いていると公言してきた私は、興奮した。その勢いのまま受諾した。
少しして10数ページの短編を書き上げ、W教諭に提出した。
お話は、真面目でシンプルはもの。
校外学習に出かけた全13台の観光バスのうちの1台が、トンネルから出てこない。トンネルの中では迷ったバスがとある屋敷の前で止まっている。車内は空っぽ。屋敷内では全員が〝虫〟になってしまっている。俺らはみんな〝勉強の虫〟?! ―ストレートやね、15歳。
漫画しか読んだことのない少年は、カフカの『変身』の情報をミミ学問で仕入れたのか、当人のくせに覚えていません(笑)
トンネルは異世界に通じる。『千と千尋の神隠し』っぽい設定は、今となっては誇らしい。
(またまた自己礼賛がすぎるゾ。笑)
私の作品が、中学生の“文芸”レベルに達していたかどうかは、わからないけどね。
いずれにしても中学校の公式冊子にマンガを掲載する。―57年前のプランとしたら、結構画期的だったろうと思う。
W先生の関与、芝居と発表会のエピソードは私の想像かもしれないが、最後のマンガ執筆の件は、直にご本人と会話したものなので、間違いのない事実である。
高校に入り、数カ月して掲載誌を一部頂戴した。
私の唯一の公刊されたマンガ作品なので家宝として永久保存すべきアイテムなのだが、わけあって紛失してしまった。
歴代の機関誌のバックナンバーが母校に残っていれば、図書室の奥や倉庫の隅…なんかにひっそりと存在しているのだろうね。